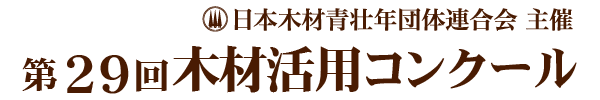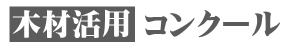木材活用コンクールは、木材の新たな利用や普及の可能性を探ることで、木材業界の発展に寄与することを目的に平成9年に創設された今年で第29回目を迎える伝統あるコンクールです。国産木材の利用促進を掲げた法整備や、SDGs・脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進む中、木材の価値と可能性は今、大きな注目を集めています。
本コンクールでは、建築物や木質空間、木製品、創造的な木材活用事例まで幅広く募集しております。木の持つ魅力を活かしつつ、未来につながる木材活用のあり方を表彰します。中でも今回は「DX賞」を新設し、設計・施工・流通・加工などの現場においてデジタル技術を活用した革新的な取り組みにスポットを当てます。技術革新による木材産業の変革や新たな価値創出に対し、積極的に評価していくことで、次世代の木材活用の方向性を提示する場となることを目指しています。
私たちは、木の文化と未来を担う挑戦を応援します。全国からの熱意あるご応募を心よりお待ちしています。
[募集要項]
[審査委員会]
※敬称略

審査委員長
深尾 精一 首都大学東京(現 東京都立大学)名誉教授
深尾 精一 首都大学東京(現 東京都立大学)名誉教授
審査委員
※五十音順
※五十音順
秋吉 浩気 VUILD株式会社 代表取締役CEO
池田 靖史 東京大学 工学系研究科建築学専攻 特任教授・建築情報学会 会長
大島 敦仁 国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室長
大西 麻貴 大西麻貴+百田有希/o+h 共同主宰・横浜国立大学大学院 教授
川原 聡 林野庁 木材産業課 木材製品技術室長
霜野 隆 一般社団法人 日本インテリアプランナー協会 顧問
竹村 優里佳 Yurica Design & Architecture 主宰
中島 史郎 宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 教授
長谷川 泰治 日本木材青壮年団体連合会 会長
宮澤 俊輔 公益財団法人 日本住宅・木材技術センター 理事長
安成 信次 一般社団法人JBN・全国工務店協会 会長
山代 悟 ビルディングランドスケープ 共同主宰・芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授
若杉 浩一 武蔵野美術大学 教授
池田 靖史 東京大学 工学系研究科建築学専攻 特任教授・建築情報学会 会長
大島 敦仁 国土交通省 住宅局 住宅生産課 木造住宅振興室長
大西 麻貴 大西麻貴+百田有希/o+h 共同主宰・横浜国立大学大学院 教授
川原 聡 林野庁 木材産業課 木材製品技術室長
霜野 隆 一般社団法人 日本インテリアプランナー協会 顧問
竹村 優里佳 Yurica Design & Architecture 主宰
中島 史郎 宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 教授
長谷川 泰治 日本木材青壮年団体連合会 会長
宮澤 俊輔 公益財団法人 日本住宅・木材技術センター 理事長
安成 信次 一般社団法人JBN・全国工務店協会 会長
山代 悟 ビルディングランドスケープ 共同主宰・芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授
若杉 浩一 武蔵野美術大学 教授
木材活用コンクールは国際社会共通の目標である
「SDGs(持続可能な開発目標)」に取り組んでいます
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()